「ゲーム依存」は小学生から
オンライン、より刺激的に-専門医が警鐘
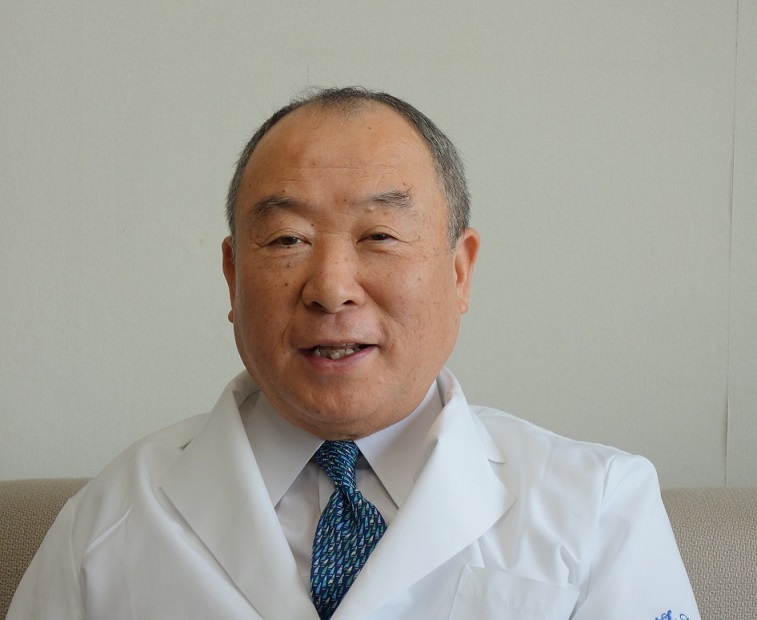
樋口進・久里浜医療センター院長
◇患者に共感示し、治療へ
現在でも、治療として確立した手法やガイドラインは存在しない。「初診の場合でも、これまで治療してきた人の中で、似たタイプや悩みを訴えていた患者はいなかったか振り返るところからが進めている。その意味では、医療としては始まったばかりの領域だ」。多くの治療経験がある樋口院長でも、治療の難しさを指摘する。
それでも今までの経験から「まずは十分に患者の話を聴く傾聴が土台になる。その上でゲームに依存している現状への患者自身が抱いている不安や懸念を少しずつ拾い上げる。そこに共感を示しながら徐々にゲームとの距離を開けるように誘導していく」と言う。
ゲームに依存している人でも、周囲を見たり自分の将来を考えたりすると、現状に疑問を抱くことがある。そういう時にうまく声をかけると、「ゲームをやめます」と反応する事例も少なくない。逆に、働きかけるタイミングを失すると、過剰な反発だけでなく、治療する側に対し攻撃的な言動で応じてしまうこともある。

ゲーム依存の子どもらが参加したキャンプ=国立青少年教育振興機構提供
◇依存度はゲーム歴の長さに比例
この依存症は、ゲーム歴が長い、つまり小学生などの時から始めている人ほど重く、治療も難しくなる。「受診者の多くは小学校や中学校からゲーム歴があり、とうとう親が連れてきた、という事例が多い。本当は掛かりつけの小児科医や学校の養護教諭が気づき、必要な相談機関に紹介する体制が必要だ」
医療的な措置とともに有効なのが、同じような問題に悩む人が集まり、ネットから切り離された環境で共同生活を経験する「キャンプ」だ。患者同士が悩みなどを打ち明けながら互いに励まし合う「ピュアカウンセリング」の一つとも言える。
同センターでも、毎年夏休み(1週間前後)や秋のフォローアップキャンプ(2泊3日)を開催し、成果を上げてる。ただこのような取り組みをしている医療機関は少なく、参加できるのは希望者の一部にとどまっている。樋口院長は「このセンターで開催している医師向けの勉強会でも、開催の半年前から希望者が定数を満たすほど、この問題に取り組もうという医師は多い。即効薬はなく、少しずつ土台をつくっていくしかない」と指摘する。(喜多壮太郎・鈴木豊)
- 1
- 2
(2019/03/10 06:05)




















