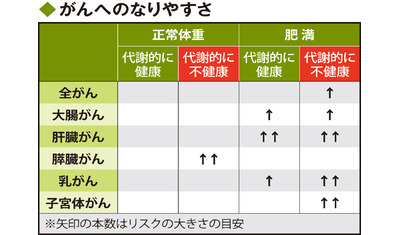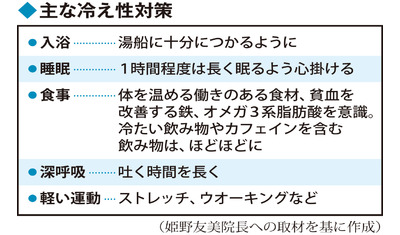障がい者の個性に寄り添う
~北京パラ競技監督の鳥居准教授に聞く~
東京パラリンピックが8月24日に開幕、各競技で熱戦が展開されている。選手たちが競技に集中し、活躍するためには、医療関係者や家族らの支えが大きい。東京保健医療専門職大学の鳥居昭久准教授(リハビリテーション学部副学部長)は、2008年の北京パラリンピックでボート競技の監督として選手の指導に尽力した。選手の障害を的確に分析した上で長所を生かし、最大の能力を生かす―。同准教授に苦心や経験を語ってもらった。

東京保健医療専門職大学の鳥居昭久・准教授
◇目的は社会参加
「リハビリを実施する立場でいろいろな人と接してきた」と鳥居准教授は言う。そもそもリハビリとは何だろうか。鳥居准教授は「障がい者も含めて病気にかかったり、けがをしたりした人たちが社会参加してもらうことが大きな目的だ」と強調する。
障がいがあっても普通に仕事ができ、スポーツもできる。スポーツをやるという目標ができれば努力する。それは趣味で絵を描いたり、楽器を奏でたりすることと同じだ。楽器を習っていて発表会に出てみたい、スポーツの大会に出てみようか。「障がいのある人が、社会参加を果たすきっかけとなるのがスポーツだったりする」と鳥居准教授は話す。
◇他者と関わるツール
他者との関わりを持つことが社会参加だ。観戦も含めてその関わりを持てるツールの一つがスポーツだと、鳥居准教授は考えている。障がい者が競技を楽しむためには、周囲のサポートが重要になる。「その人に何ができるか。どこまでできるかを見極める。そして、できそうな事を見つけ、そこから始めていく」
固い信念を持ってやらなければならないと考えるのは、つらい面もある。「車いすで近くの公園を回ってみようかと思い立つのも社会参加のきっかけになる」鳥居准教授。趣味であるスポーツで「せっかく始めたのだから、大会を目指して頑張ってみようか」と練習を重ねた結果が、パラリンピック出場につながることもあるだろう。

北京パラリンピックに向けたダブルスカルの練習=2008年、戸田漕艇場で
◇選手によって異なる指導
各地の障がい者スポーツセンターでは、日本障がい者スポーツ協会が認定する「障がい者スポーツ指導員」が活動している。ただ、鳥居准教授は「競技でより上を目指したいという選手のためにトレーニングを指導したり、コンディションを整えたりすることができる人は意外に少ない」と指摘する。「アスレチックトレーナー」(日本スポーツ協会認定)に匹敵する形で、09年から「障がい者スポーツトレーナー」の養成が始まったのも、こんな背景がある。現在、200人弱が有資格者だ。
強化指導は個々の選手が置かれた状況によって異なる。「これ以上続けても強くならないのではないか」と限界を感じる選手もいる。そんなときは「こんなふうにしたら強くなるかもしれないよ」と、新たなトレーニング法を提案することもあるという。
片方の足に義肢を着けているために、体幹のバランスが悪い選手もいる。「誰にでも身体のくせがある。どこの部分が弱いかは人によって違う。これは障がい者のスポーツに限ったことではない」。さらに競技の特性が加わることから、どこが使えて、どこが使えないのかといった点をきちんと分析する必要がある。
ボート競技は08年の北京パラリンピックで採用された競技だ。鳥居准教授は、選手たちを支援しようと手伝ったのがきっかけで急きょ、監督を務めることになった。ボートのシングルスカルの選手は、腕と肩の力だけでこぐ。一方、体幹が使える選手が出場するダブルスカル(男女ペア)は上半身全体を前後に動かしてこぐ。舵手(だしゅ)つきフォアは4人でこぎ、視覚障害のある選手も出場する。

ダブルスカルの選手の体をケアする鳥居准教授
◇手作りしたシート
鳥居准教授は、北京パラに向けてダブルスカルの選手を指導。「障がい者スポーツのコーチは初めてだったが、私自身が大変勉強になった」と振り返る。健常者の場合は、こちらがスポーツの方に合わせることが多いが、障がい者の場合は一律にスポーツの方に合わせることはできない。『この人はどうやったら、ボートをこげるか』という異なる視点と発想が求められる。
ペアの1人は左足の股関節から下が無く、もう1人は右足の膝から下が無かった。踏ん張る足が異なると、オールを引っ張るときの傾きに差が生じてしまい、ボートが蛇行する。鳥居准教授は、2人がボートを真っすぐに進めるためのトレーニング法を研究するとともに、骨盤がゆがんでいくのを防ぐために専用のシートを手作りした。
◇選手支援の在り方
スポーツは夢を与えてくれるが、時には挫折感や無力感をもたらす。「一番になれるのは1人しかいない。きれい事だけで済まない面もある。そこを理解した上で、『トップにはなれなかったけれど、ここまで出来たじゃないか』と支援することも必要だ」と言う。
高校野球をやっている少年全員が甲子園に出場できるわけではない。しかし、野球をやる楽しさは変わらない。鳥居准教授は「少しでもスポーツをやって良かったと思ってくれればよい。それが私たちのやりがいになる」と力を込めた。(了)
(2021/08/31 05:00)
【関連記事】