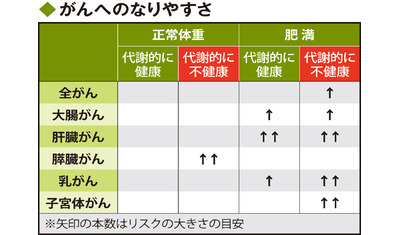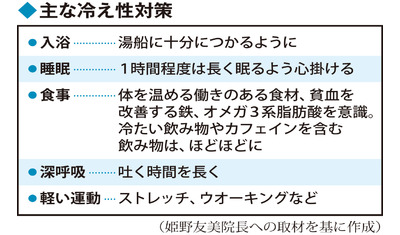内視鏡検査・治療の進歩=胃がん死亡率低下に貢献

内視鏡や支援機材の改良が進んだことも診察時の患者の負担軽減と診察精度の向上を果たしている。昔は、大人の親指よりも太い光学ファイバーを患者が強い吐き気を我慢して飲み込み、35ミリフィルムで患部の写真を撮影するだけの文字通りの「胃カメラ」だった。しかし、現在は鼻の穴から食道に入れられるほどの細さの物が普及している。機能も、操作する医師にリアルタイムで鮮明な画像を届けるだけでなく、ポリープなどの組織の採取、精密検査が必要な部分などに色素を吹き付けて染色することもできるようになっている。
この点について河合教授は「機能の多様化に加え、画像の解像度や色の再現性も向上したことで早期の病変部を示す非常に微妙な変色なども、ある程度経験を積んだ医師であれば鑑別できるようにまでなった」と指摘する。早期の胃がんの発見率では、造影剤を使ったX線画像検査に比べて大きく優位に立っている、という。
河合教授によると、胃がん発病のリスクを高める細菌であるピロリ菌を胃から駆除する治療が健康保険で認められ、胃の内視鏡検査が義務付けられた2013年に、胃がんの死亡者数に変化があったという。「それまでの数年は年間5万人前後だったのが、14年以降は4万6000人前後にまで減少している。治療法の進歩もあるが、内視鏡検査で早期に発見できた患者が増え、結果的に死亡者の減少につながったのではないか」とみている。
◇東京23区で相次ぎ導入
このような事情を反映して、市町村などが実施している胃がん検診について、これまでのX線画像検査に内視鏡検査を加え、受診者が選択できるようになった自治体も増えている。「金沢市や新潟市など先進的な自治体もあったが、ここ数年で東京23区の中で世田谷区や杉並区、目黒区などが相次いで導入している。この傾向が広がり、都内である程度の数の自治体が導入すれば、導入自治体が全国に広がるきっかけになるかもしれない。そうなれば胃がん早期発見の確率は大きく向上し、今以上に完治が期待できる『比較的怖くないがん』になるのではないか」と同教授は話す。
内視鏡検診の普及は、診療所やクリニックなど小規模医療機関への内視鏡導入の呼び水になり、より多くの医師が内視鏡検査についてのスキルを磨く機会を得ることを意味する。ただ、内視鏡の操作や映し出された画像の評価は医師一人一人の経験と能力に左右される部分があるため、診療結果は医師によるばらつきが生じてしまう側面もある。
この点について河合教授は「検診として内視鏡検査をすれば、検査画像を他の医師にもチェックしてもらう必要が生じ、当然、問題があれば指摘されることになる」と予想。その上で、他の医師からの指摘を受け続ける環境が出来上がれば、画像の評価や内視鏡の操作について「誰かに見られている」という意識を持ち、自然に正しい操作法や評価法を学ぶことにつながる、と期待している。(喜多壮太郎・鈴木豊)
- 1
- 2
(2018/02/04 16:00)