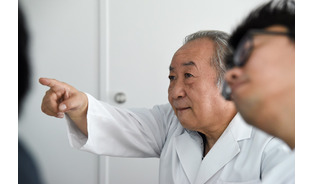一流に学ぶ 難手術に挑む「匠の手」―上山博康氏
(第5回)退院指示に教授激怒=「術者プライド」13年かけた教育
順風満帆に研修医生活を送っていたある日、都留教授が机をひっくり返して怒るようなことをしでかしてしまった。上山氏は教授を心から尊敬していたし、目をかけてもらっている自負もあった。しかし教授が執刀予定だった患者を、同氏は独断で退院させたのだ。患者は第三脳室(脳の中心部)の奇形腫(テラトーマ)で入院していた9歳の女児。手術前の週末、病院外の喫茶店に両親を呼び出し、こう切り出した。
 「3年前、同じ病気の子が手術後に植物状態になって、半年後に亡くなっています。僕があなたたちにしてあげられるのは唯一、退院させることです。病院にいて医者という立場だったら『帰れ』とは言えない。でも、今は私服で病院の外だから」
「3年前、同じ病気の子が手術後に植物状態になって、半年後に亡くなっています。僕があなたたちにしてあげられるのは唯一、退院させることです。病院にいて医者という立場だったら『帰れ』とは言えない。でも、今は私服で病院の外だから」
研修医1年目に初めて受け持った患者も、同じ9歳の女児だった。上山氏にはその時の悲しい思い出が重なった。
「今でもはっきり覚えてますよ、意識がボーっとした状態で入院してきてね。当時はCT(コンピューター断層撮影装置)なんてないから、針を刺して腫瘍を見つけるんです。なかなか麻酔が効かなくて、『我慢してね』というと『うん』と言って。骨に穴を開けて皮膚を縫って、ドレープっていう紙をはいだら、大きな目が涙であふれているの。我慢して。かわいいでしょ」
上山氏が手術でシャントという管を入れる処置をしたら、元気になって病室を動けるようになった。ただ一人の受け持ち患者だったこともあって、絵本を読んであげるなど、看護師詰め所から文句が出るほど病室に入り浸っていた。それが手術後に植物状態になってしまった。上山氏は泊まり込んで看病したが、意識は戻ることなく亡くなった。
「無理して腫瘍を取らなければ寝たきりにならなかった。取れもしない腫瘍とともに意識も命も取ってしまった。僕は都留先生を恨んでいました。研修医の立場で、治療方針に口を挟むなんてことはできない。だから2人目は、僕が真剣にこの子に何をしてやれるか考えた時、帰してやることだけしか思いつかなかった」
- 1
- 2
(2017/10/12 08:19)