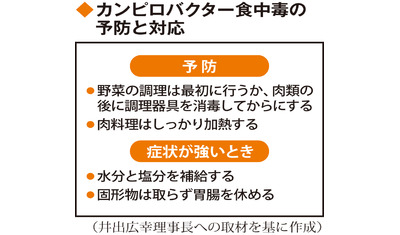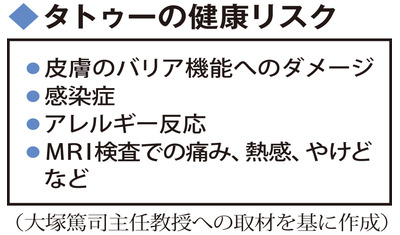あなたもがんをみとる=死に直面する厳しさ
かつては「不治の病」というイメージの強かったがん。検診の普及による早期発見の確率が高まり、治療法の進歩もあって、治癒(完治)する事例も増えてきた。しかし、進行して増殖したがん細胞が他の臓器にまで広がる「遠隔転移」(用語解説参照)してしまうと、限られた種類のがん以外では、多くの場合完治が期待できず、患者や家族らは「死」に直面せざるを得ないのも、現実だ。
「昔に比べてがんに関する知識も広まり、『がんで亡くなる』ということを隠すようなこともなく、『珍しくはない』と周囲に受け止められてきているのは確かです」。ホスピスや緩和ケア病床、在宅で多くのがん患者をみとり、現在は東邦大学医療センター大森病院(東京都大田区)緩和ケアセンター長の大津秀一医師は現状をこう語る。
◇有効な時間過ごす
 「昔と違い、支持療法(用語解説参照)の効果で抗がん剤の強い副作用やがん自体の痛みで苦しむ中で死を迎えることが減り、患者は最期の数週間まで見た目には大きな変化なく生活できるようになり、旅行や家族・友人との語らいなどに有効な時間を過ごすことができます」。大津医師は、痛みを和らげる緩和ケアや抗がん剤の副作用を抑える支持療法の成果が確実に広まっている、と力説する。
「昔と違い、支持療法(用語解説参照)の効果で抗がん剤の強い副作用やがん自体の痛みで苦しむ中で死を迎えることが減り、患者は最期の数週間まで見た目には大きな変化なく生活できるようになり、旅行や家族・友人との語らいなどに有効な時間を過ごすことができます」。大津医師は、痛みを和らげる緩和ケアや抗がん剤の副作用を抑える支持療法の成果が確実に広まっている、と力説する。
しかし、そのような状態が最期まで続くことはない。強い倦怠感や食欲の低下に始まり、筋力の低下によりトイレに一人で行けなくなったり立ち上がれなくなったりといった活動量の低下が続く。このような変化に患者も家族も当惑しているうちに、意識が薄れて起きているのか眠っているのか分からない状態や、時間や空間の認識が難しくなる「せん妄」という状態が、8割近くの患者に生じてしまうという。
◇遠隔転移への理解
 「どんなに緩和ケアの技術が進んでも、最期を迎える直前の数週間から数日は、どうしても厳しい状態に陥る」。患者は体調の激変に戸惑い、不安になり、本来の意思とは反する言動を取ってしまうこともある。周囲の家族はそのときの発言や態度が、死を迎えて表に出た患者の本心だと思い、患者の死後も引きずる心の傷を負ってしまう。大津医師は「このような状態は死を迎えるまでのごくありふれたプロセスです。事前に主治医や訪問診療医から家族に説明することが大切になります」とアドバイスする。
「どんなに緩和ケアの技術が進んでも、最期を迎える直前の数週間から数日は、どうしても厳しい状態に陥る」。患者は体調の激変に戸惑い、不安になり、本来の意思とは反する言動を取ってしまうこともある。周囲の家族はそのときの発言や態度が、死を迎えて表に出た患者の本心だと思い、患者の死後も引きずる心の傷を負ってしまう。大津医師は「このような状態は死を迎えるまでのごくありふれたプロセスです。事前に主治医や訪問診療医から家族に説明することが大切になります」とアドバイスする。
ただ、前提として「自分には有効な治療法が無く、死を待っている状態だ」という現実を患者や家族が受け止める必要がある。最近は緩和ケアや支持療法が充実し、ある日、突然体調が悪化し始めるため、急変後の短い時間の中で患者や家族が受け入れられないことが少なくないからだ。
がんの終末期患者の多くは、「完治=生存」が望めない遠隔転移という状態と診断された後、生活の質を保持した延命のための抗がん剤治療を続ける。使える抗がん剤が無くなると緩和ケア医療を受けながら余命を過ごす―というパターンを踏む。ところが、多くの患者や家族は、この遠隔転移という診断を正しく受け止められているのかどうか疑問だ、という指摘もある。
- 1
- 2
(2017/11/12 13:41)