一流に学ぶ 難手術に挑む「匠の手」―上山博康氏
(第12回)戦う相手、人から病気に=最後のとりで、患者に「大丈夫」
手術時間を少しでも短縮させるために、さまざまな工夫をしている。北大時代に開発した水の出る吸引管もその一つ。足のペダルで操作して、片手で手術部位からの出血を洗浄、吸引しながらもう片方の手では別の作業が進められる。
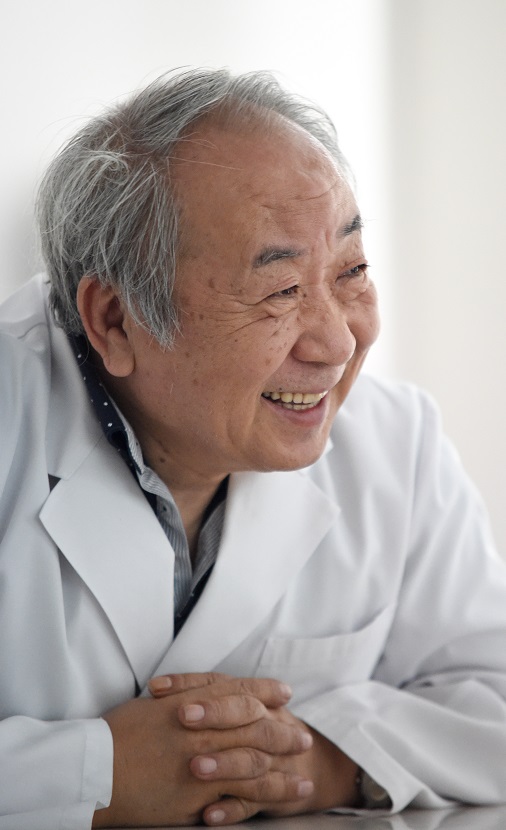 「この器械も改良を重ねて、今や4代目。進歩をやめたら、すぐに追い抜かれる。常に新しいモデルを開発していかなければ、この世界ではトップを走れません」
「この器械も改良を重ねて、今や4代目。進歩をやめたら、すぐに追い抜かれる。常に新しいモデルを開発していかなければ、この世界ではトップを走れません」
自身の手術手技を高める努力は言うまでもない。医師になってから約10年間、利き手の右を封印し、左手で箸を使い、字を書いた。そのおかげで、いちいちハサミや器具を持ち替えることなく、スピーディーに処理ができる。
考えられる限りの努力を重ねた結果、全国からさじを投げられた患者を救う最後のとりでになったのだ。
「手術で治せると思ったら、大丈夫って言い切ります」と上山氏。患者の多くが、その言葉を耳にするなり涙を流すという。手術前のインフォームドコンセントと言えば、ありとあらゆるリスクを説明され、かえって手術を受けるのが怖くなるという人が多い。患者が最も聞きたい「大丈夫」という言葉を口にする医師は今日、ほとんどいないと言っていいだろう。
「もしも患者を救えなかったら、家族から訴えられるかもしれませんよ」とスタッフは心配するが、実際、患者から訴えられたことは一度もないという。
そんな上山氏の奮闘ぶりが、2006年、NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」という番組で放映されると、さらに全国から患者が集まり、礼状や激励の手紙が段ボール箱がいくつも埋まるほど届いた。
「夜中に奥さんと一緒に整理していたら、ポツリと言ったんです。『あんた教授になれなくて良かったね』って。ならなくて、じゃなくて、なれなくてって。もし言ったのが奥さんじゃなかったら殴りますよ」と笑う。「大学にいた8年間は見守っていて、すごく切なかったって。旭川行ってからは、のびのび仕事していましたから、奥さんが見ていて、明らかにどっちが幸せか分かったんでしょう」(ジャーナリスト・中山あゆみ)
→〔第13回へ進む〕手術失敗も「放映を」=1年後、確認できた奇跡
- 1
- 2
(2017/11/30 10:52)





















