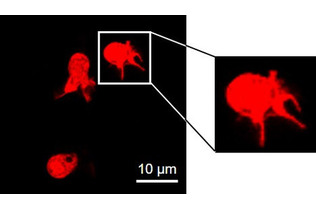イタリア・Centro di Riferimento Oncologico di Aviano(CRO) IRCCS/University of UdineのRossana Roncato氏らは、薬物療法開始前の遺伝子検査による副作用軽減について検討した国際多施設非盲検ランダム化比較試験PREPAREの二次解析を実施。その結果、フルオロピリミジン系抗がん薬またはイリノテカンによる治療を行った消化器がん患者のうち、治療前のDPYD/UGT1A1遺伝子検査でActionable変異の保有者と判定され用量調節を行った者では、標準治療を行った者と比べて臨床的意義のある毒性作用のリスクが90%低下し、入院および関連費用も減少したとJAMA Netw Open(2024; 7: e2449441)に発表した。
対照群の7.4%、介入群の6.7%がActionable変異保有者
解析対象は、イタリアでPREPARE試験に登録され、フルオロピリミジン/イリノテカンによる治療を受けた18歳以上の消化器がん患者563例(年齢中央値68.0歳、男性56.3%、対照群311例、介入群252例)。対照群では全例に標準治療を行った。介入群では、DPYD/UGT1A1のActionable変異保有者に対してオランダ薬理遺伝学ワーキンググループ(Dutch Pharmacogenetics Working Group;DPWG)のガイドラインに基づく用量調節を行い、非保有者には標準用量を投与した。
対照群の311例中23例(7.4%)と介入群の252例中17例(6.7%)がActionable変異保有者だった。
主要評価項目は、臨床的意義のある毒性作用〔フルオロピリミジン/イリノテカンと因果関係があると判断され、米国立がん研究所(NCI)有害事象共通用語基準(CTCAE)version 4.0に基づくグレード4以上の血液毒性有害事象、グレード3以上の非血液毒性有害事象、入院を要する有害事象〕とした。
毒性リスクと関連費用が大幅減、治療強度は影響なし
年齢と性を調整後の多変量ロジスティック回帰分析の結果、対照群のActionable変異保有者と比べ、介入群のActionable変異保有者では主要評価項目の発生リスクが有意に90%低かった(34.8% vs. 5.9%、調整後オッズ比0.1、95%CI 0.0~0.8、P=0.04)。
追跡期間中に 毒性作用により入院したActionable変異保有者は、有意差はないものの対照群で多かった(34.8% vs. 11.8%、P=0.12)。また、Actionable変異保有者1例当たりの毒性作用の管理費用は、介入群(26ドル、95%CI 0~312ドル)と比べて対照群(4,159ドル、同1,510~6,810ドル)で有意に高かった(P=0.004)。
3年全生存率は有意な群間差がなかったが、質調整生存年(QALY)は介入群で有意な改善が認められた(P=0.001、Mann-Whitney test)。
以上を踏まえ、Roncato氏らは「消化器がん患者に対する治療前DPYD/UGT1A1遺伝子検査に基づくフルオロピリミジン/イリノテカンの用量調節は、治療の強度には悪影響を及ぼさない一方で、標準治療と比べて安全性の向上、入院および関連費用の減少をもたらす可能性が示された」と結論している。
(医学翻訳者/執筆者・太田敦子)