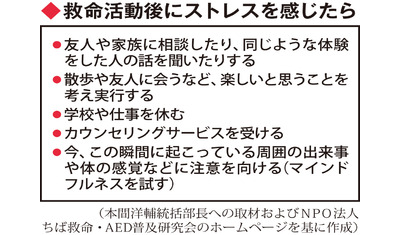なぜ多い夏休み明けの自殺
子どもの変化に気を付けて
東京医科大学茨城医療センター精神科科長の桝屋二郎准教授は児童精神科の専門医として、福島大学の「子どものメンタルヘルス支援事業推進室」で震災や原発事故での被災児への支援に携わってきた。そうした経験を踏まえ、「中学生以下の子どもの自殺は大人とは違う点がある」と感じてきたという。
枡屋二郎東京医科大学准教授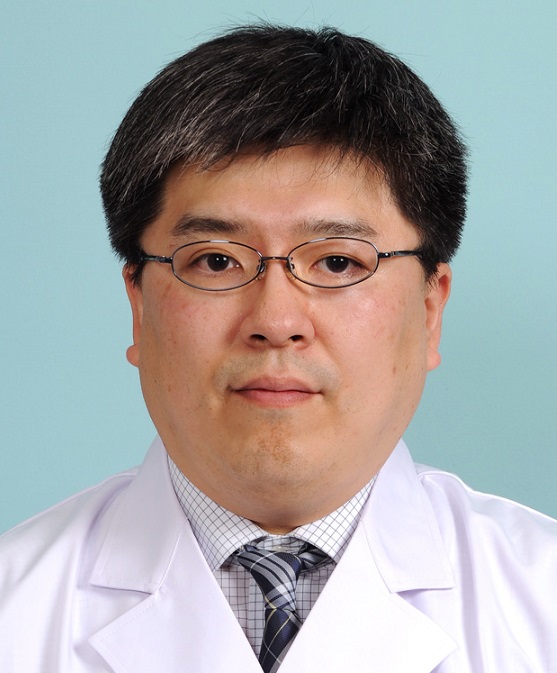
その一方、社会全体で希薄な対人関係が珍しくない中で、人生経験の浅いこの世代は、友人との仲たがいや失恋、仲間はずれにされるといった対人関係などのストレスへの耐性が低く、対処するすべを持たないため、抑うつ状態や適応障害に陥る確率が高くなり、その分自殺のリスクが高くなってしまう。
「それでも、『つらい』とか『何もしたくない』などといった言葉を発する。また、食事を取らなかったり、部屋に引きこもったりと、日常と異なるサインを出せる子どもは、まだ対処ができる。しかし、このようなサインすら出せずに追い詰められてしまう子どもも少なくない」と枡屋准教授は話す。
この問題が比較的明確に出るのが、不登校問題。学内でのいじめや環境への不適応などさまざまな理由はあっても、実際に学校に通えなくなる不登校の子どもはいわば、サインを出している。それに対して周囲からの登校することを求める圧力や自身の「学校には行かなければならない」という意識から、どんなにつらくても学校に通おうとしてしまうのがサインを出せない子どもだ。「無理して通っていた子どもにとって、夏休みはいわば〝執行猶予〟のようなものだ。新学期が近づくと、自分を追い詰めることになる」と、そうした子どもたちの気持ちを代弁する。そして「不登校を選択できているから、自殺を回避できている子どもたちが多い。不登校の子どもたちに登校を促すことは有効な場合もある反面、不用意に行うと、自殺のリスクを高めかねないもろ刃の刃であることを社会はもっと知るべきだ」と訴えている。
こんな場合にどう対応したらよいのか。まず、保護者や学校の教師が子どもの安心できる環境を整えた上で、「何でも話していい」「君のことを大切に思っている」「死にたくなるのだったら、学校に通わなくてもいい」などというメッセージを子どもたちに発信し続け、「相談してもいいな」という信頼を得ることだ。桝屋准教授は「相談を受けた後は、保護者や教師だけで事案を抱え込まず、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、養護教諭など専門的な心理支援の技能を持つ専門家につなぎ、チームとして長期的な支援をしていくべきだ」とアドバイスする。
◇不安感じたら専門医に
ただ、全国全ての学校でこのような連携がスムーズに進むとは限らない。緊急を要すると感じられた場合は、信頼できるかかりつけ医に相談して児童精神科の専門医を紹介してもらい、一度診察を受けることも考えてほしい。
「かかりつけ医からの紹介状があった方が動きやすいが、全ての医師が児童精神医学に通じているとは限らない。事情によっては、原則予約診療の医療機関でも、急患として受け入れることはある。数は少ないが、児童思春期精神領域の専門医に直接相談して診てもらうこともできる」と、いざという時の備えを説く。
背景には、思春期の児童生徒の心の不安定さがある。心身の発達にバランスが取れていない状態におかれて精神的に不安定になる「思春期うつ病」という特有の病態もある上、双極性障害や統合失調症の発症の最初のピークでもあるからだ。
「本当に自殺しようと思う段階で心は何らかの病的状態にあることが多い。それが短期的なものなのか、背景に大きな病気があるのかは簡単に分からない。不安に感じたら専門医の診察を一度受けてもらえば、必要な支援のネットワークにもつなぎやすい」。桝屋准教授はこう呼び掛けている。(喜多壮太郎・鈴木豊)
- 1
- 2
(2018/09/02 16:00)