こちら診察室 つらくない手術を目指す
「神の手」からシステムへ
~進歩する手術前後の医療~ (医学博士 谷口英喜)【第1回】
もし自分が病気になったと考えたとき、まず病気自体や治療によるつらさを思い描くでしょう。特に医師から「手術が必要です」と宣告されると、以前に手術を受けた人から聞いた痛みや吐き気など、嫌な思い出だけが思い浮かぶこともあるでしょう。このため、「手術がうまい」「手術をせずに治す」などとうわさされる遠方の「名医」を訪ねる、という話はよく耳にします。首都圏のクリニックを受診すると、「神の手」と言われている医師をPRする小冊子が置かれている光景が見られます。
しかし、時代は変わりました。現在では、そういう「名医」に頼らずに全国どこにいても、システムとして患者をサポートすることで、つらくない手術治療を受けられるようになりつつあります。このシステムとその基本となる考え方は「術後回復能力強化プログラム」といい、2000年頃に北欧諸国で発案されました。この連載では、手術の前後を通じて患者の負担軽減を目指す取り組みを紹介します。

手術にはつらいというイメージが付きまとう
◇手術の日から飲水OK
このプログラムの方針は一貫しています。医学的根拠(エビデンス)に基づいた行為を手術とその前後の治療に携わる医療スタッフがチームとなって実施することです。具体的な例の一つとして、治療生活を特別な環境とせず、日常生活の側面をできるだけ残しながら、手術を含めた治療が実施されることがあります。
胃がんの治療で胃の切除手術を受ける場合を考えてみましょう。従来の管理法では、胃を空にしておくために手術の前の夜は完全に絶食してもらい、午後9時以降は水分の摂取も禁止です。さらに下剤を服用してもらうとともに、水分などを補給するための点滴が始められます。手術が終了しても栄養補給は点滴による管理が続き、手術後24時間がたつまでは飲食禁止です。手術後につらいこととして、「喉が渇いて仕方が無かった」と言う話を耳にします。その後、ようやくおかゆを食べることができ、通常の食事に戻るには数日かかります。
一方、術後回復能力強化プログラムでは、手術前夜の夕食まで軽食にはなりますが、通常の食事ができ、水も手術前に麻酔をかける2時間前まで飲むことができます。下剤も必要最低限とし、点滴はしません。手術後もその日から水は飲めますし、翌朝からはペースト状の栄養剤を口から摂取することも始めます。患者の負担はどちらが少ないかは、一目瞭然でしょう。術後回復能力強化プログラムは食事制限の期間が短く、点滴も不要、下剤による負担が軽いなど、患者負担が少なくなっています。点滴が不要になれば、ケアを担当する医療スタッフの負担軽減にもつながります。
◇つらさ、不安を和らげる
この飲食制限の変化で、従来の手術を受ける患者のつらかった点が改善されています。麻酔導入の2時間前まで水が飲めるようになったことで、患者の喉の渇きや不安感を和らげられます。
また以前は、胃だけでなく、腸の中もきれいにするために強い下剤を服用してもらっていました。手術中に腸に便があると手術がやりづらいので強力な下剤で排出させていたわけです。それが、大腸の右半分から直腸にかけての手術以外は、軽めの下剤でよくなりました。これにより、下剤による不自然な排便や腹痛の負担が軽減できています。
他にも、医療従事者たちが通気性の悪い予防衣を身に着け、蒸し暑く感じられたために手術室は冷房を効かせていました。だから、麻酔がさめた患者がとたんに震え(シバリング)を起こすことがありました。手術中は加温機を使い、術後の病室も室温を管理しながら布団も暖めておくことで、寒さや震えの苦痛を回避できます。結果として、血液の固まる力(凝固力)や免疫力も高めることにつながります。
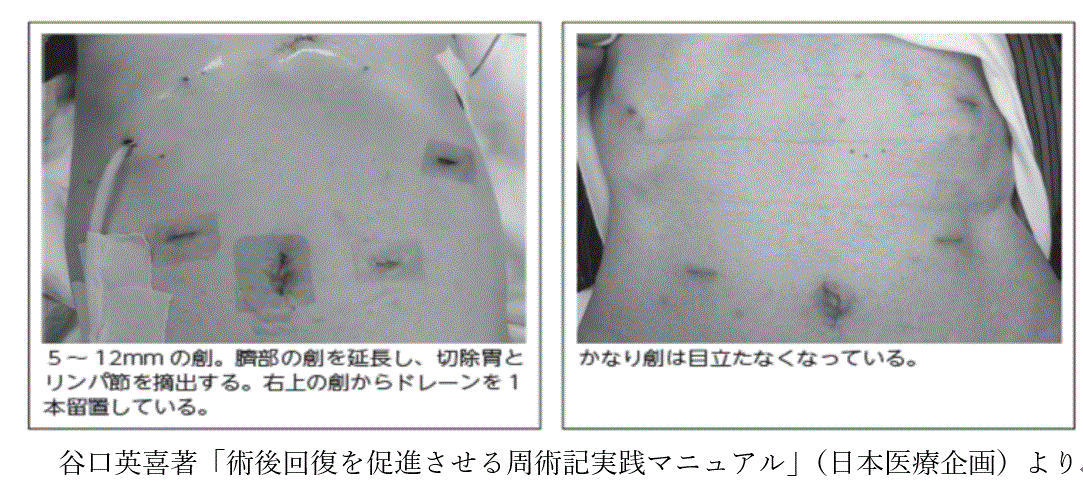
胃がんの手術直後(左)と1か月後。1カ月後は傷跡(創)があまり目立たない
◇「DREAM」で早期退院へ
術後の管理も、胃管や尿道カテーテルなどの管類を長期に入れておく場面を減らして可能な限り早く抜去すれば、患者の自由度が向上し、管を入れている痛みから解放されます。また痛みや吐き気を抑える薬を予防的に投与することで術後の痛みや吐き気を減らしたり少なくしたりすることができれば、その分、患者の苦痛が軽減できるだけでなく、可能な限り、早く動かせることで合併症の減少にもつなげることができます。
その他にも、このプログラムの導入で変わった項目は多数あります。腹部や胸に大きな切れ目を入れて、中の臓器にたどり着く手術法よりも、腹腔(ふくくう)鏡やダヴィンチなどの手術用ロボットの支援を得て、小さな傷口で手術を済ませる手術法を選ぶことや、麻酔薬を作用時間の長い薬から短い薬にすることで患者の意識回復を早める、手術後に安静を求めるのではなく、早期に活動を始めるようにして日常生活への復帰を促すなど、さまざまな変化を指摘できます。
実際に、このプログラムを導入することにより、術後にすぐに飲み始め(Drinking)、食べ始め(Eating)、動き始める(Mobilizing)ことが可能になります。この英語の文字をつないだ「DREAM」が胃など消化器外科分野の手術後1~2日目で達成できれば、術後回復が促進され早期に退院できることが明らかになっています。
◇変わる医療の世界
これまで、こうしたことができなかった理由は、昔からの風潮に従って患者を管理することに医療関係者の誰もが疑いを抱かなかったことにあります。さらに言えば、大病院を舞台にしたテレビドラマ「白い巨塔」ではありませんが、先輩医師の言うことには逆らえない時代が長く続いてきたからです。言い換えれば、現場で「これ、ちょっと違うんじゃないの?」と思っても、決して口に出すことができなかった時代だったからとも言えるでしょう。
それが変わったのは、科学的根拠(エビデンス)に従った医療が患者の治療を円滑に進め、より多くの命を救えることが明らかになったからだと考えられています。さらには、主治医だけではなく看護師や他の医療職なども加わるチーム医療という考え方が広まり、より多くの眼を持って評価されることが標準化され、昔のように科学的根拠に基づかず、医師個人の経験だけに基づいた医療行為は許されない時代となったためでもあるのでしょう。
術後回復能力強化プログラムの効果指標は、合併症の発生率の減少、安全性の向上、在院日数の短縮の三つです。この三つの成果を達成することは、医療費の削減にもつながります。特に在院日数の短縮による医療費削減の効果は大きいでしょう。このプログラムは、国の医療費負担が大きく、個人の医療費負担が少ない欧州において医療費削減のために考案されたシステムです。英国では、プログラム実施施設に対してインセンティブを支払い、国家的な医療戦略として国内に広がっています。
一方、日本での普及は未だ十分ではなく、プログラムを実施する施設と非実施施設における格差拡大が生じてしまっています。現在の日本は医療経済も逼迫(ひっぱく)しており、コロナの感染拡大により病床不足も露呈されました。それらを解決する切り札として、このプログラムの普及をきっかけにしたいと考えています。(了)
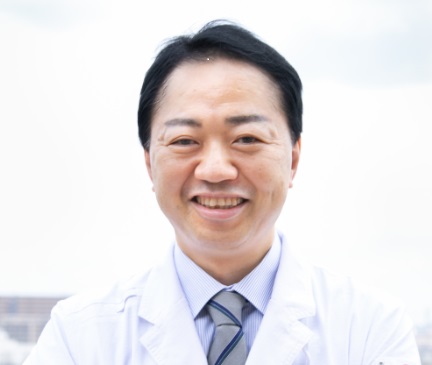
谷口英喜医師
谷口 英喜(たにぐち・ひでき)
麻酔科医師 医学博士
済生会横浜市東部病院 患者支援センター長兼栄養部部長。1991年、福島県立医科大学医学部を卒業。専門は麻酔・集中治療、経口補水療法、体液管理、臨床栄養、周術期体液・栄養管理・チーム医療など。麻酔科認定指導医、日本集中治療医学会専門医、日本救急医学会専門医、東京医療保健大学大学院客員教授。テレビ、ラジオに多数出演。年に1冊のペースで、水電解質、経口補療法に関する著書を出版。2021年には「はじめてとりくむ水電解質管理 上下2巻」を刊行。
ウェブサイト
(2022/03/23 05:00)
【関連記事】





















