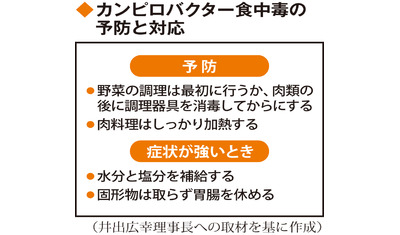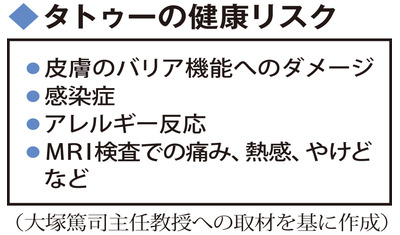子どもの意識変え、社会を変えるがん教育を =現場の言葉で伝えたい―林和彦東京女子医大がんセンター長
「がん教育」に取り組む小・中・高校が少しずつ増えている。東京女子医科大学がんセンター長の林和彦教授は、外部講師として授業に出向き、実践を重ねるトップランナーの一人。「がんの知識を付けるのではなく、防災や人権の教育と同じように、がんに対する意識を変える教育をしたい」と語る。
◇授業聞いた生徒、母親の闘病明かし決意
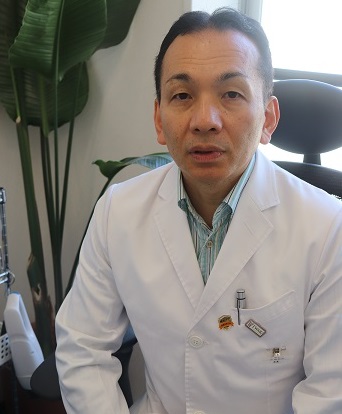 「林先生、きょう一日、がんのことについて、詳しく教えてくれてありがとうございました」。10月、東京都内の中学校に出向き、3年生2クラスの保健体育の授業で「がん教育」を行ったとき、生徒会長がみんなの前でお礼の言葉を述べた際の様子を、林教授は学校や生徒本人、保護者の了解を得て、自らのがん教育のブログ「『がん』になるって、どんなこと?」に紹介している。
「林先生、きょう一日、がんのことについて、詳しく教えてくれてありがとうございました」。10月、東京都内の中学校に出向き、3年生2クラスの保健体育の授業で「がん教育」を行ったとき、生徒会長がみんなの前でお礼の言葉を述べた際の様子を、林教授は学校や生徒本人、保護者の了解を得て、自らのがん教育のブログ「『がん』になるって、どんなこと?」に紹介している。
「実は僕の母親ががんになって、今も放射線治療を続けていて…」「きょうはそのことも詳しく教えてくれて本当にありがとうございました」「授業の最後に、家族の力が何よりも大切だということを教えてもらったので、僕はこれからもしっかりと母親を支えて、きょうの話を生かしていきたいと思います」―。
林教授は「先生方も(母親の闘病公表という)想定外のカミングアウトに泣いてしまいました」と振り返る。
家族ががんで闘病中だったり、亡くなったりしている子どもたちがいる場合、がん教育の実施に当たって、どのような配慮が必要なのか―。林教授が一番多く受ける質問だ。林教授は原則として、学校を事前訪問してできる限りの打ち合わせを行い、児童・生徒へのアンケート結果に目を通してから本番に臨む。保護者にもがん教育の事前通知をしておくよう、学校側にアドバイスしている。
この学校では、生徒の母親の闘病について把握しており、授業に参加させるか、あいさつを担当させるか悩んでいた。「無理をしなくていい」と本人や保護者に伝えたが、本人たちは前向きだったという。ただ、母親に関する告白は思わぬ展開だったそうだ。
がん教育では、小児がんの当事者がいる場合は格段の配慮が必要だ。この学校のような家族のがんに関するケースについても、林教授は「実際の現場では正反対の状況(授業などに前向きでない状況)も十分あり得る」と事前の配慮を求め、打ち合わせへの注意を促す。その一方で、生涯のうち2人に1人はがんになる時代であり、過度の配慮は「あまり意味がない」と考えている。「おばあちゃんが膵臓(すいぞう)がんで亡くなった、お母さんが乳がん、といった子どもがいることを前提に授業をすればよい。がんは怖いというだけで終わらず、正しいことをきちんと知らせる必要がある」
実際、がん患者が子どもの家族にいるケースを、学校側が事前に把握しようと思っても「子どもがいじめられる」「他の保護者と気まずくなる」といった心配から隠していることが多く、がん教育後の保護者らの集まりで「実は…」と打ち明けられるケースによく遭遇するという。
(2017/12/03 12:12)