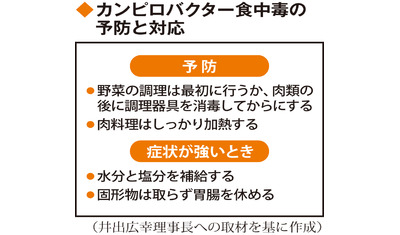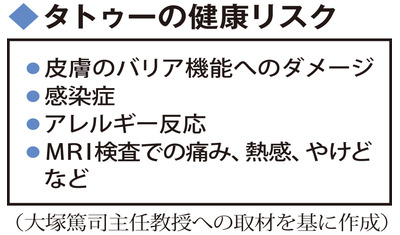患者の心に寄り添う=神経眼科、若倉雅登医師に聞く
「視覚とは眼球と脳の共同作業(インタラクション)だ」。井上眼科病院(東京都千代田区)名誉院長で、神経眼科という分野をけん引してきた若倉雅登医師はこう語る。目の症状を診るだけが眼科医の仕事ではない。目の病気に苦しむ患者の心の不安に寄り添うこともまた、眼科医の大切な役目だと訴える。
◇頭の回路が不調
 ―2016年に開催した神経眼科学会の特別講演では、まぶたを開けにくくなる眼瞼(がんけん)けいれんを取り上げた。診察する患者の約40%はこの病気だという。
―2016年に開催した神経眼科学会の特別講演では、まぶたを開けにくくなる眼瞼(がんけん)けいれんを取り上げた。診察する患者の約40%はこの病気だという。
若倉 眼瞼けいれんは重症化すると、まぶたを開けたくても開けることができなくなる。学会での講演は私の最終講演、引退講演とも言うべきもので、千数百例のデータを発表した。まばたきがうまくできなくなる。これはまぶたという運動系の問題であると同時に、まぶしいとか痛いとか、ショボショボするとかいった感覚過敏の問題もある。しかし、一般の眼科医はドライアイや眼精疲労、アレルギーといった目の表面の病気だと診断することが多い。実はこの病気は脳の病気で、脳の回路が不調になっている。
◇情報の9割近く目から
若倉 快適な形で物を見るためには能率的に脳の機能を使わなければならない。それは成長するとともに自然に備わっていくことが、赤ちゃんの成長を見ていると良く分かる。ある研究によると、脳に入る情報の87~88%は目から入る。残りが耳(聴覚)、鼻(嗅覚)、手(触覚)などだ。視覚がいかに大切か、ということを示している。
日本とは医療や福祉の水準が異なる発展途上国では、視覚を失うと死に直結することがある。「眼科医は患者の死の危険と関係ないのでいいですね」と言われることがあるが、それは違う。視覚を失えば大きなダメージを受け、生活が困窮してしまう。そんな眼科の特殊性が軽視されているところがある。
◇置き忘れた心の問題
―仕事をしたり、普通に暮らしたりする上で鍵となる器官が目。眼科の医師には、患者の「心の問題」という課題にも向き合う必要がある、という。
若倉 「目が見えにくくなってきた」とか「目に不快感がある」といった症状を抱え眼科を受診する患者は、病名を聞きに来たわけではない。治るのか、治らないのか。治らないとすれば、どうやって生活したらよいのか。10年後にはどうなっているのか。最も知りたいのはその答えなのにもかかわらず、医師は参酌してこなかった。
病気で視力が悪くなったとき、元の正常な状態に戻すことはほとんどできない。患者は不安感を持つ。抑うつ状態になり、眠ることができないこともある。これまでの眼科医が関心を持っていなかった心の問題にも関わっていかなければならない。
◇盟友と研究会発足
―健康を損ねた患者の心の叫びにどう応えていけばよいのか。考えた末に、杏林大医学部付属病院眼科の気賀沢一輝氏と二人で心療眼科研究会を立ち上げた。
若倉 研究会では毎年1回、症例を紹介したり、精神科や心療内科の医師らから話を聴いたりしている。2016年は発達障害に関するテーマを扱った。
参加者の3分の2は眼科医で、開業医が多い。大学病院の医師らより関心度は高い。看護師や視能訓練士らも参加し、熱心に聴いている。目の疾患に関係する周りの問題について、医師は扱いきれない。しかし、彼らは患者を目前にするため関心を持たざるを得なくなる。
人間は毎日、目で物を見る。その目の働きの不十分さを毎日体験しているのに、理解して助けてくれる人がいない。患者は「どうしてよいか分からない。生きているのがつらい」と感じる。精神科医や心療内科医にかかっても「眼科に行きなさい」と言われる。病状を患者に理解してもらい、心のケアにも当たるのも眼科医の仕事だ。
◇救われる患者
―患者側の反応はどうだろうか。
若倉 「ようやく自分のことを分かってくれる医師にたどり着いた」「これまで無視されてきたが、症状を分かってくれた上でこちらが理解できるように説明してくれた」―と、喜んでもらえる。患者の苦しみを分かるだけで、患者は半分くらい救われた気持ちになるのではないか。
私は緑内障や加齢黄斑(おうはん)変性症などを患い、心を病んでいる人たちも診ている。ほとんど失明に近い患者もいる。症状の進行を遅らせたり、10年後に少しでも物が見えたりするような治療をしているが、元に戻るわけではない。将来の希望が見えないと、患者側は本当に不安だ。それなのに、医師側は紋切り型の処置でおしまいにしてきた。
―視覚障害に対し、日本の医療や福祉はどうなのか。
若倉 日本の福祉は冷たい、と感じることがある。うつ病の患者に対してはそれなりのケアをしてくれるのに、視覚障害のために抑うつ状態になったり、不眠になったりする患者は助けてくれない。目が痛かったり、まぶしかったりして毎日の生活が困難なのにもかかわらず、障害者と認定されない。彼らはうつ病と同じような厳しさを抱えているのに。
まぶたが開かないのは、失明と同じ状態だ。しかし、無理にまぶたを開けて「視力は1・0」で正常などと判定する。言ってみれば、「数値至上主義」に陥っている。
◇初の試みに挑む
―新たな試みとして2015年、目の悩みや不調を抱える人たちに適切な助言を与える組織としてNPO法人「目と心の健康相談室」を立ち上げた。大学病院眼科病棟主任看護師や井上眼科病院看護部長の経験を持つ荒川和子さんが理事長を、若倉医師が副理事長を務める。
若倉 電話による相談が主体だが、場合によっては対面相談にも応じる。こういう組織は日本で初めてではないか。会員制で入会金は3000円、会費は半年間で6000円だ。可能ならより低額で運営したいが、医療にはお金がかかることを実感してもらうという、社会実験の意味もある。
スタッフは真剣に対応する。患者も真剣に相談する。プロが相談に乗るためには、お金をもらわなければならない。患者側がこれに賛同してくれれば、この相談室のような組織が普及していくだろう。
◇患者から見えてくるもの
―後輩の医師たちへのメッセージは。
若倉 若い時には研究などに没頭するのもよいだろう。一方で、医師の原点に返り、患者を少しでも助け、プラスになることは何かを考えてほしい。患者に寄り添ってこそ初めて見えてくるものがある。それは、教科書には載っていない感受性、想像力の問題だ。
―初の単行本「目は快適でなくてはいけない」から、明治の女性医師をテーマにした「茅花流しの診療所」まで執筆活動も旺盛だ。
若倉 現在は1日に診る患者を25人に限っている。40年間に及ぶ医師生活で医療に対する誤解、医療の抱える矛盾も見えてきた。今後は自らのコンセプトに沿った診療を続けながら、得た知識を一般の人たちに向けて発信していきたい。
(聞き手は解説委員・鈴木豊)
(2017/01/13 14:42)