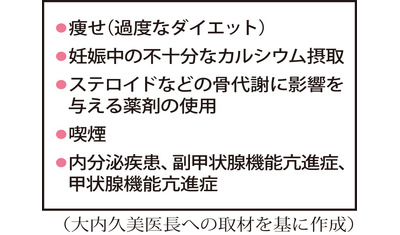「一人酒」はアルコール依存症の要注意サイン=患者への望ましい対応は―成瀬暢也埼玉県立精神医療センター副院長
◇心配なのは定年男性、早めの治療を
男性の場合、飲酒リスクで成瀬副院長が特に心配しているのは高齢者だ。定年退職を引き金に、飲酒が増えるケースが目立つという。「仕事熱心だった男性が、その役割をなくした空虚感から飲酒し、アルコール依存症になってしまう」と、典型的なパターンを紹介する。
仕事から引退し、家族と過ごす時間が増えてもコミュニケーションをうまく取れない。かといって、趣味もなく、デイサービスの施設に通うわけでもない。孤独と暇をもてあまして酒に頼ってしまう―。そんな高齢男性は、超高齢化社会の進展とともに、さらに増える恐れがありそうだ。
介護の現場でも、アルコール依存症の高齢男性にどう向き合うのかが課題となっている。「酔えば転倒もしやすい。さまざまな要因で認知症にもなりやすくなる」と成瀬副院長。そうした観点からも、早めに飲酒のリスクに気づき、治療や予防などの対応を取ることの大切さが浮かぶ。
ところが、まだ軽度の依存症や予備軍の段階で受診する人は、あまりいないのが実情。依存症に対する偏見もあり、精神科のアルコール専門外来の敷居は高い。こうした壁を打ち破るためには、「アルコール依存症は病気だ」という意識改革が、本人を支える周囲の人はもちろん、治療者側にも必要だと、成瀬副院長は訴える。
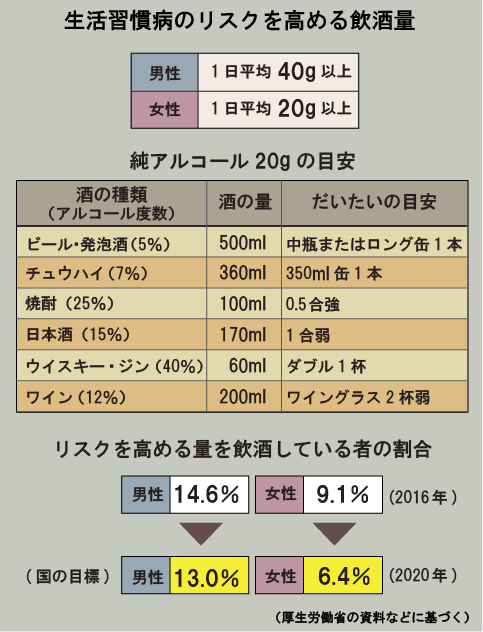 「がん治療にたとえれば、これまでは末期がん患者だけ治療対象になっているようなもの。もっと早期から介入しなければならない」。その手段の一つとして、米国精神医学会による最新の診断基準「DSM5」に基づき、「アルコール使用障害」という概念でこの病気をとらえ、従来の依存症治療よりも早期の段階から治療対象とするよう提案する。
「がん治療にたとえれば、これまでは末期がん患者だけ治療対象になっているようなもの。もっと早期から介入しなければならない」。その手段の一つとして、米国精神医学会による最新の診断基準「DSM5」に基づき、「アルコール使用障害」という概念でこの病気をとらえ、従来の依存症治療よりも早期の段階から治療対象とするよう提案する。
治療する側として思い描くのは、軽症の使用障害なら、うつ病のように精神科の一般外来での治療が当たり前になり、内科などの身体科でも糖尿病や高血圧対策をモデルに飲酒量チェックなどの初期介入を行うという「治療革命」だ。
(2017/10/15 14:01)