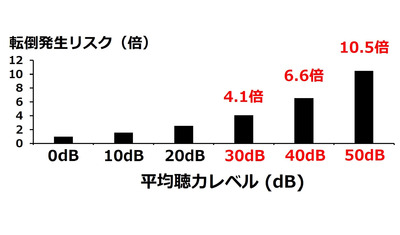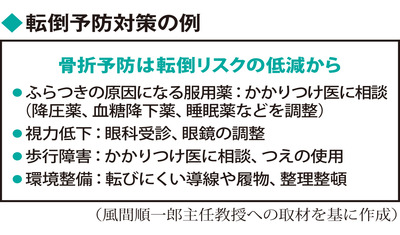相談しにくい「トイレの話」
~下痢や腹痛で就労に影響―炎症性腸疾患~
炎症性腸疾患(IBD)は小腸や大腸などの消化管に炎症が起きる病気の総称だ。原因が分からない「非特異性炎症性腸疾患」で、クローン病や潰瘍性大腸炎などがある。下痢や腹痛、急にトイレに駆け込みたくなる症状は大変つらい。問題は治療法の進歩で就労継続はできるのに、職場で伝えにくいことだ。専門医やIBD患者を支援するNPO法人は、雇用する企業と従業員のコミュニケーションが何より大事だと強調する。

北里大学北里研究所病院の小林拓・炎症性腸疾患先進治療センター長
◇働き盛り世代に多い病気
IBDは近年、急増傾向にあり、30~40代の「働き盛り世代」に多いとされる。IBDのうちクローン病の主な症状は、初期に最も多い下痢や腹痛に加え、血便、体重減少、発熱などだ。小腸と大腸のいずれか、または両方で炎症が起きる。潰瘍性大腸炎の主な症状は、下痢や血便、便意切迫、腹痛などだ。重症の場合は体重減少や発熱、貧血などを引き起こす。潰瘍性大腸炎の炎症は直腸から口側に広がっていく。
北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センターの小林拓センター長は、IBD治療を専門としている。IBDの原因は分からないものの、小林センター長は「食事の欧米化や腸内細菌、免疫応答の異常で誤って腸を外敵として攻撃してしまうことなどが背景にあるのではないか」とみている。
継続的な治療やきちんとした日常のケアによってかなり良い状態を維持できるようになった。小林センター長は治療の進歩を踏まえた上で「薬を使って炎症をコントロールするだけでは患者に幸せをもたらせない。そういうもどかしさを感じている。治療と就労との両立も重要だ」と話す。
◇やりがいある職場退職
20代の男性は就職直後に潰瘍性大腸炎を発症した。仕事が休めないために通院が不定期になり、服薬もおろそかになった。薬がなくなったが、受診希望日に予約が取れず、そのまま通院を中断してしまった。3カ月に症状が悪化し、結局、入院する事態になった。
30代前半の女性は大学卒業後、食品会社に就職。試食をしながら商品を開発する仕事にやりがいを感じていたが、28歳の時にクローン病を発症した。症状はコントロールされていたが、食事制限が必要だと考え、試食する商品を選ぶことができない職場を退職した。
40代の男性は16歳の時にクローン病を発症し、入退院を繰り返した。大学には進学しなかった。20代半ば以降、症状は落ち着いている状態(寛解)にあるが就職はせず、家業を少し手伝う程度だ。母親が作った食事以外を摂取することはほとんどない。

IBDネットワークの仲島雄大・就労特任理事
◇患者は病状伝え、企業は環境整備
IBD患者の生活の質(QOL)改善や治療と就労の両立などを目指し、尽力しているのがNPO法人「IBDネットワーク」だ。就労特任理事の仲島雄大さんは潰瘍性大腸炎に罹患(りかん)してから30年以上になり、「これまでの人生の半分以上は病気だが、これも自分の『性格』だと考え、やっとこの病気を受け入れられるようになった」と話す。
子どもの頃から自動車が好きで、自動車整備士養成校教員の道を選んだが、潰瘍性大腸炎を発症。下痢や下血、体重減少などに苦しむようになった。しかし、病名を正確に診断できる医師に出合わず、「胃腸炎だ」と診断されてきた。トイレに行く回数は増え、通勤の途中でトイレに立ち寄れる場所を決めていた。大学病院を受診し、医師から「潰瘍性大腸炎かもしれない」と告げられた時、「病名が付いたことで、少し前向きになれた」と振り返る。
トイレまで我慢できずに、便を漏らしてしまったらどうしよう。そんなことを会社の上司や同僚には相談しにくい。患者たちの大きな悩みだ。
適切な治療を続ければ、寛解を維持して仕事を続けることができる。雇用する側は、IBDを患う従業員が定期的に通院でき、症状が悪化したときにはすぐに受診を認める。仲島さんは「企業はそういう環境を整えてほしい」と訴えるとともに、「当事者がどのような配慮が必要かを分かりやすく伝えることも必要だ」と指摘する。大事なのは上司と当事者の日頃のコミュニケーションだ。「上司が一言声を掛けてくれるだけで、ハードルは下がる。当事者の企業の配慮を当たり前と考えず、『ありがとう』と感謝の気持ちを伝えてほしい」と言う。(鈴木豊)
(2024/07/24 05:00)
【関連記事】