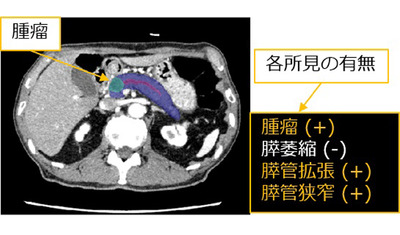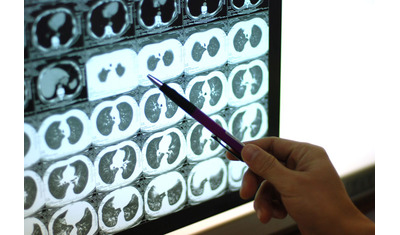「医」の最前線 AIと医療が出合うとき
「ブレイン・コンピューター・インターフェース」
~AIが脳とコンピューターの接続を加速~ (岡本将輝・ハーバード大学医学部講師)【第7回】
「ブレイン・コンピューター・インターフェース」(BCI)という言葉を聞いたことがあるだろうか。これは脳とコンピューター(やその他の外部機器)との間にアルゴリズムを介した通信リンクを提供するもので、簡単に言うと「脳とコンピューターをつなぐ技術」となる。
元は重度の運動障害を持つ人々を支援するため、脳とコンピューターの直接通信の確立を目指した試みが中心だった。特に医学領域では、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の意思疎通や四肢欠損・まひ患者の運動支援を狙った研究が盛んであったが、近年は適用範囲が拡大し、思考によるマルチコプターの操作(※1)や人型ロボットの駆動(※2)、仮想現実(VR)の制御(※3)に至るまで、多様な応用研究が見られるようになっている。
また、2016年にはイーロン・マスク氏がNeuralink社を設立し、BCI領域への参入を明らかにしたことでも話題を呼んだ。20世紀半ばから連綿として続くBCI研究および開発が、ここ10年で急進した背景には深層学習をはじめとするAI技術の向上がある。今回は、脳とコンピューターをつなぐこのBCI技術を概説した上で、注目すべき先端研究の一例を紹介したい。

BCI大会に向け準備する、電極スカルキャップを着用した半身不随のパイロット=2016年10月スイス=EPA時事
◇BCIを構成するもの
BCIを実現させるための重要な要素として(1)生体信号の取得(2)信号の処理と解釈(3)接続先のデバイス-の3点がある。仮に今、上肢欠損患者を支援するためのロボットアームを開発したいとする。患者がボールをつかみたいと思ったとき、意志に合わせて人の手のようにスムーズに動く義肢だ。厳密には、このような「脳と機械の接続」は「ブレイン・マシン・インターフェース」(BMI)と呼ばれるが、現在ではBCIとほぼ同義として扱うことができる。
このロボットアームを実現するには、まず意志を拾うための生体信号を取得する必要があるが、これには脳波が広く活用されてきた。脳波は「脳の電気活動」を計測するもので、1920年代にBergerが報告した古典的技術となる。また、脳波のBCI活用を最初に体系的に試みたJ. J. Vidalによる取り組みも70年代のことであり、いずれも長い歴史を持っている。医学領域ではできるだけ「身体侵襲の低いこと」が求められるため、BCIにおける信号取得も、脳への電極埋め込みなどを必要としない非侵襲的手法が中心となっている。近年では、機能的近赤外分光法(fNIRS)、脳磁図(MEG)、機能的磁気共鳴画像(fMRI)、機能的経頭蓋ドップラー超音波など、医用画像モダリティの多様化に伴ってさまざまな信号取得が検討されている。
ノイズ(アーチファクト)が少なく、再現性の高い良質な信号が確保できれば、次はこれを解釈するアルゴリズムが必要になる。一般的な脳波測定では、頭部外表から脳神経細胞の活動によって生じる微少な電気活動を捉えるため、侵襲性は低い一方で「多数の細胞による活動集合」が記録されるという限界を持っている。したがって、脳波波形から情報の選別を行い、特定の情報を取り出すことは容易ではなかった。近年の機械学習、特に深層学習技術の向上は、このような波形解析の限界を突破することに貢献しており、自律的な学習によって波形画像から高精度な情報抽出を実現している。
アルゴリズムを介して解釈された情報(例えば「手を開きたい」)は、接続先のデバイスにあたる末梢(まっしょう)のロボットアームに伝達され、意図する動きが再現される。BCIが代表するブレーンテックの飛躍的な成長には、AI技術の進歩とともに、このようなロボット工学および計測技術の向上もまた大きな役割を果たしている。

脳とコンピューターをつなぎ、外骨格を動かす。ロボット義足などを使った身体障害のあるアスリート=2016年10月スイス=AFP時事
◇BCIの先端事例
BCIの可能性を実感できるものとして、米スタンフォード大学の研究事例を一つ紹介しておきたい。これは21年にNature誌(※4)から公表された研究成果で、「脳内で想像した手書き意図を神経信号から読み取り、高速でテキスト変換する」という技術だ。書字動作を脳内で想像した際の「運動皮質における神経活動」を解析し、PC上での高速なテキスト入力に置換するAIシステムを開発した。脊髄損傷により四肢まひのある患者において、毎分90字を94.1%の精度でタイプすることができ、汎用(はんよう)のオートコレクト機能を用いることで、その精度は99%を超えたとしている。
これは一般的なスマートフォンでの入力速度に匹敵しており、脊髄損傷や脳血管疾患後の制限されたコミュニケーション機能を支える基礎技術となる可能性があるため、この成果は大きな注目を集めた。なお、大学公式ウェブサイト上で、実際の文字入力の様子を動画で確認することができる。ぜひ参照していただきたい。
脳のダイナミックスが本質的には神経生理学的に不安定であり、刻一刻と著明な変化をもって出力されるため、BCIは特に信号取得とその処理に種々の技術的課題を抱えている。また、BCIを継続運用することによる身体および精神的影響や倫理面の議論・評価の余地も多分に残されている。一方、上に示した先端事例に見られるように、BCIは脳とコンピューターの接続を可能にすることで、これまでには見られなかった全く新しい技術を生み出し、人々の生活を支え、拡張する可能性を持っている。今後同領域がどのように発展し、どのように人類の健康に寄与していくのか、その関心は高まる一方だ。(了)
【引用】
(※1)LaFleur K, Cassady K, Doud A, et al. Quadcopter control in three-dimensional space using a noninvasive motor imagery-based brain-computer interface. J Neural Eng 2013; 10:046003. doi: 10.1088/1741-2560/10/4/046003
(※2)Spataro R, Chella A, Allison B, et al. Reaching and grasping a glass of water by locked-in als patients through a BCI-controlled humanoid robot. Front Hum Neurosci 2017; 11:68. doi: 10.3389/fnhum.2017.00068
(※3)Vourvopoulos A, Pardo OM, Lefebvre S, et al. Effects of a brain-computer interface with virtual reality (VR) neurofeedback: a pilot study in chronic stroke patients. Front. Hum. Neurosci. 2019; 13:210. doi: 10.3389/fnhum.2019.00210
(※4)Willett FR, Avansino DT, Hochberg LR, et al. High-performance brain-to-text communication via handwriting. Nature 2021; 593:249–254.

岡本将輝氏
【岡本 将輝(おかもと まさき)】
米マサチューセッツ総合病院研究員、ハーバードメディカルスクール・インストラクター、The Medical AI Times編集長など。2011年信州大学医学部卒、東京大学大学院医学系研究科専門職学位課程および博士課程修了、University College London(UCL)科学修士課程修了。UCL visiting researcher、日本学術振興会特別研究員(DC2・PD)を経て現職。他にTOKYO analytica CEO、SBI大学院大学客員准教授(データサイエンス・統計学)、東京大学特任研究員など。データアプローチによる先端医科学技術の研究開発に従事。
(2022/07/20 05:00)
【関連記事】