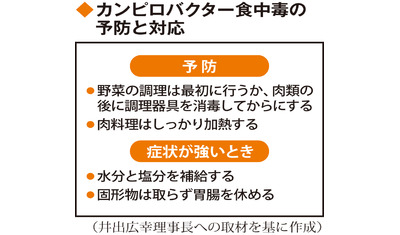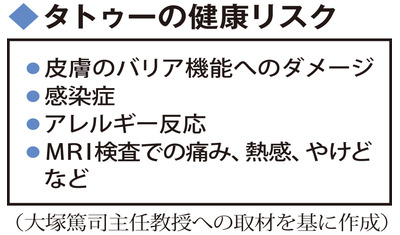終わりなき病原体との闘い
感染症専門医の拡充を―舘田一博東邦大教授インタビュー
新型コロナウイルスの感染拡大と対策の遅れは、感染症に対する日本の危機意識の低さを浮き彫りにした。パンデミック(世界的大流行)は今後も予想され、コロナが収束した後も、薬剤耐性菌問題など感染症をめぐる課題は尽きない。日本感染症学会の前理事長で、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードのメンバーでもある舘田一博東邦大医学部教授に、コロナと向き合った1年半と今後の課題について聞いた。
◇繰り返す波

「感染症に強い社会をつくっていかなければ」と話す舘田一博教授
「第2波の真っただ中」。2020年8月、舘田教授が日本感染症学会学術講演会の会長講演で当時の感染状況に触れた言葉が翌日の全国紙1面の見出しになった。同年5月下旬に緊急事態宣言が解除されてから再び感染者数が増加傾向にあったにもかかわらず、政府は「第2波」という言葉を避けていたからだ。
「実際に第2波の真っただ中だったからね。それを政府が言わない理由もよく分からなかった」。当時、感染者数自体は多くなかったが、その後も感染拡大の波は繰り返し、21年7月の現在、東京五輪・パラリンピックを目前に控えて再拡大している。
「これはもう第5波と言っていい。この感染症は早めに対策を打って、減少に転じさせないといけないが、変異株が広がり、自粛疲れで市民の協力も得にくい。一筋縄ではいかない」
今、国内でも広がっているインド由来の「デルタ型変異株」は、従来のウイルス(中国由来)の約2倍感染力が強いとされる。
「病原体は遺伝子を残すために感染が広がりやすく変異していくものなので驚くことではない。風邪の原因となるコロナウイルスは4種類あるが、新型コロナも長い目で見れば5番目の風邪のウイルスになるかもしれない」と指摘する。
その上で、「02年にSARS(サーズ=重症急性呼吸器症候群)、12年はMERS(マーズ=中東呼吸器症候群)、そして今回の新型コロナのパンデミックが起きた。また何年かしたら同じような感染症が来る。危機管理の視点で検査体制やワクチン、治療薬について備えていかないといけない。それをやれなかったら、僕たち専門家の責任です」と力を込める。

4回目の緊急事態宣言が発出され、感染拡大防止を呼び掛ける東京都の職員ら=2021年7月12日、東京都新宿区
◇専門医の不足
日本感染症学会は、新型コロナの感染拡大の当初から、感染対策や治療、ワクチンに関する考え方などの情報を発信する一方、感染症専門医の育成や活用について国に要望してきた。
同学会が認定する感染症専門医は、現在約1600人。「本当は3000人ぐらい必要だがなかなか増えない。大学の医学部に感染症学講座を設置して感染症専門医を育てて、その人たちが中心となって感染症対策、感染症診療を行う仕組みをつくらなければいけない」と舘田教授は言う。
具体的にはどうすればいいのか。「例えば1000床以上の病院には感染症科をつくらなければならないと政府が決めればいい。感染症の専門医が他の診療科の患者に関する相談を受けたら病院に診療報酬が発生し、政府が補塡(ほてん)する。そういう仕組みがあれば感染症専門医を雇うことができる。その代わり何かあったときには病院内だけでなく地域の感染対策をやってもらうのです」

衆院内閣委員会で意見陳述する舘田教授=2021年1月29日、国会内
感染症研究の遅れは、ワクチンや治療薬開発の取り組みの遅れにもつながった。「製薬会社だけに任せるのではなく、大学がやっていかなければならない」と指摘する。「大学に感染症科があり、教授やスタッフがいて、研究も教育も診療もやるという仕組みがあれば、今回のようにはならなかった」と言う。
背景にあるのは危機管理と安全保障の視点の甘さだ。「アメリカやヨーロッパは炭疽(たんそ)菌やエボラウイルスによるバイオテロなども考えて研究を進め、その成果をmRNAワクチンに応用したから対応が速かった。日本は研究開発に投資をしてこなかったから、10年の差が出てしまった」
その結果、日本は海外のワクチンに頼らざるを得ず、接種も遅れた。「自分の国にワクチンを持っていないのはつらいですよ。アメリカや英国は自国民優先。日本は戦略を間違えていたんです」
◇尽きない課題
舘田教授は長崎大学出身だ。江戸時代も海外に開かれていた長崎は、歴史的にも地理的にも感染症との関わりが深く、同大学は長年にわたって感染症研究に力を注いできた。舘田教授は感染免疫学に興味を持ち、サッカー部の先輩だった賀来満夫・東北医科薬科大学特任教授に誘われて感染症分野を志したという。がんの撲滅が大きな社会的課題で、感染症研究の道を目指す学生が多くなかった時代だ。
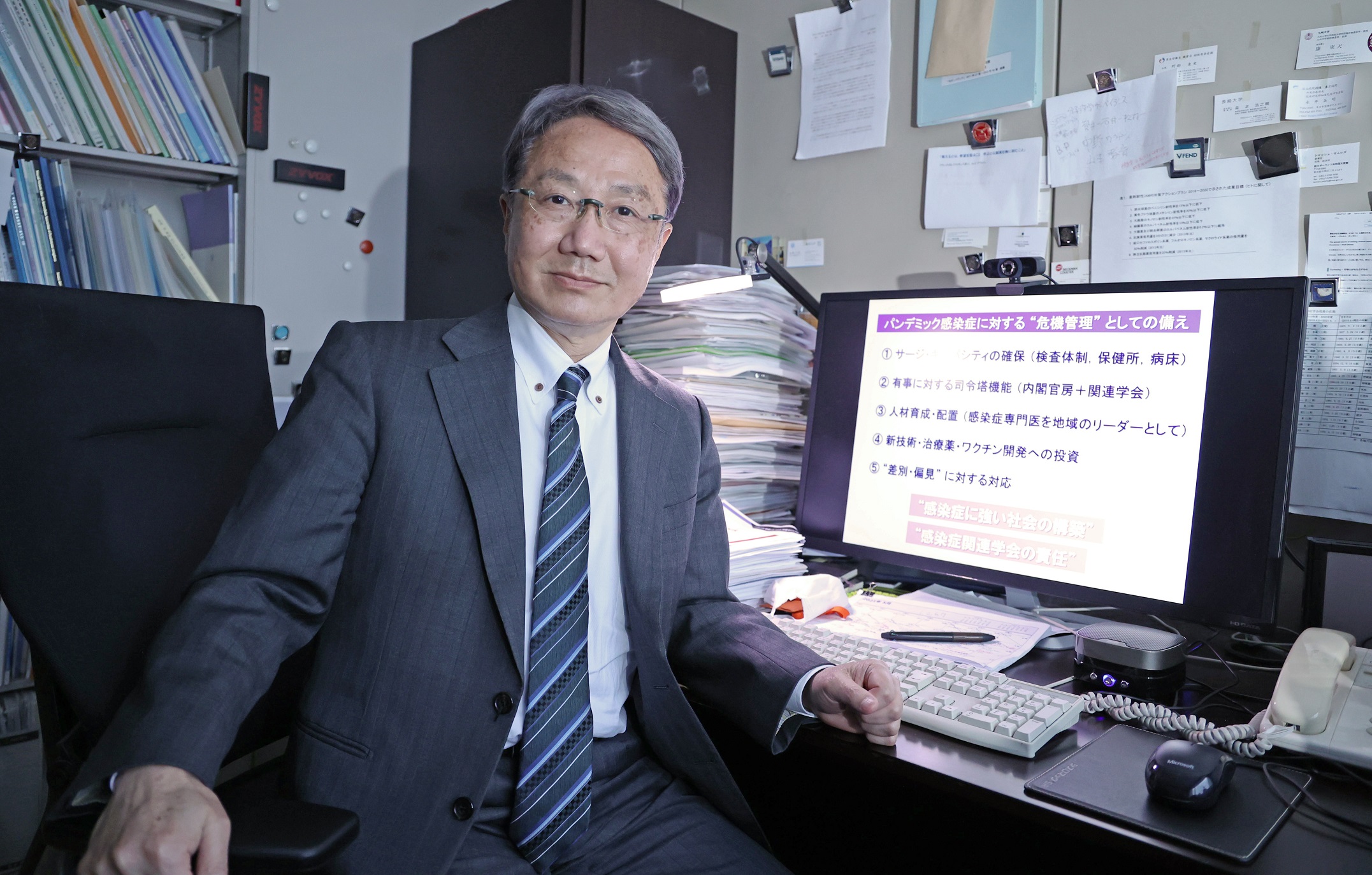
「こういうパンデミックは必ずまた来る。医学を志す人は命の不思議についてリサーチマインドを持ち続けてほしい」と語る舘田教授
「感染症は、自分がかかるかもしれないし、自分が人にうつすかもしれないが、病原体というはっきりした原因がある。そして、それが変化し、進化していくという不思議がある。パンデミックで広がる可能性があるからグローバルな視点もある」と研究分野としての魅力を語る。
エイズやエボラ出血熱などの新興感染症や、臨床現場で進行している薬剤耐性菌の問題など課題は尽きない。「薬剤耐性菌の広がりは(知らないうちに進行する)サイレントパンデミックと言われ、50年には1000万人が亡くなるのではないかと言われています。コロナが落ち着いたら、またクローズアップされる。どんな薬が創られても抑えることができない病原体との闘いがあるんです」
2期4年務めた日本感染症学会の理事長としての最後の1年はコロナ禍と重なった。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長や、国立感染症研究所の脇田隆字所長らと共に感染状況などについてさまざまな形で発信してきたが、限界も感じた。「医療の立場から感染症を考えて、こうした方がいいと言うのは、ある意味、簡単なんです。1カ月間一歩も外に出ないようにロックダウンして、鎖国のように海外からも人を入れなければ、たぶん、感染症は収まりますよ。最初の段階でそれをやればよかった」

プロ野球とJリーグに感染症対策を助言し、表彰された(左から)舘田教授、三鴨廣繁・愛知医科大学大学院教授、賀来満夫・東北医科薬科大学特任教授=2020年12月17日、東京都港区(代表撮影)
だが、それでは社会と経済へのダメージが大きい。「あの時、僕たちは鎖国すべきとは言えなかった。今みたいな状況になるとは思わなかったから。新型インフルエンザのパンデミックの時、『大変だ』と言いながら、そうならなかった。また同じように空振りする可能性があったからだ。正しく評価し、正しく恐れることは難しい」と振り返る。
09年の新型インフルエンザパンデミックへの対応を総括した報告書の中には、保健所機能の充実や、創薬、ワクチンなどについて課題が示されていたが、十分に生かされていないという。「このパンデミックが収まったときには、今回の反省を基に次に備えなければならない。10年後までには必ず来るわけだから。また同じようなことでは話になりません」(了)
(2021/07/17 05:30)
【関連記事】