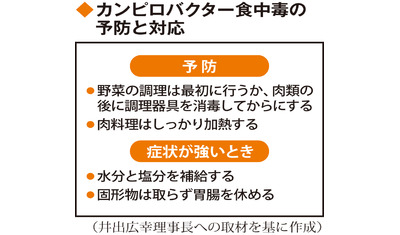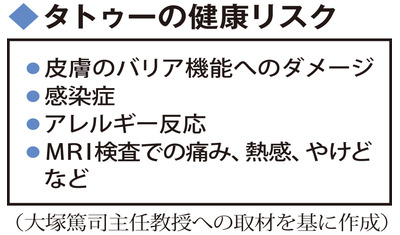妊娠中のママ接種で赤ちゃん守る
~乳児用RSウイルスワクチン、まもなく現場に~
ほぼ全ての子どもが2歳までに感染するとされるRSウイルス。せきや鼻水といった風邪症状をはじめ、肺炎や細気管支炎にまで発展することもある。特に生後6カ月未満だと重症化しやすく、入院が必要になる場合も比較的多い。有効な治療法や特効薬がない中で、米製薬大手ファイザーが開発した母子免疫ワクチンがこのたび、日本国内で初承認。6月までに発売されるのを前に同社が開催した報道向けセミナーで、今後期待されることなどを専門医が語った。

ワクチンについて「基礎疾患のない子へのアプローチが高まる重要なポイントになる」と話す森岡医師
◇入院児の多くは基礎疾患のない子
「小児科医にとってRSウイルス感染症は、インフルエンザや新型コロナウイルスより重症化しやすい疾患と認識している」と話すのは、日本大学医学部小児科学系小児科学分野の森岡一朗医師。日本では、毎年約12万~14万人の2歳未満の乳幼児が同感染症と診断され、約4分の1が入院を必要とすると推定されているが、対症療法しか手だてがない。
早産児や慢性肺疾患・先天性心疾患のある乳児、ダウン症候群の乳児は、重症化しやすいと言われる。こうしたリスクの高い子には抗体薬の使用が認められ、2002年に保険適用、一般診療で使えるようになった。
東京都内と近郊の12施設で18年に行われた、RSウイルス感染症の入院実態調査によると、基礎疾患のある子の入院数は全体の5%以下。抗体薬の効果が高いことが示された一方、同ウイルス関連で入院する子どものほとんどが、基礎疾患のないことが分かった。「特に生後6カ月未満の低月齢で健康な子たちが多く、どうにかしたいと考えていた」と森岡医師は話す。
◇ママに接種、おなかの赤ちゃんへ
米食品医薬品局(FDA)は23年8月、ファイザー社開発のRSウイルスワクチンを承認したと発表。日本でも今年1月に承認された。
妊娠24~36週の妊婦に1回接種し、その後、母親の体の中で作られた抗体が、胎盤を通して胎児に移り、同ウイルス感染症の発症や重症化を防ぐ仕組みだ。

倉澤医師は「産婦人科もワクチンの知識を深めていく必要がある」と話す
国際的な臨床試験を踏まえた国内初の承認。ワクチン接種によって①RSウイルスが原因の体調不良や下気道疾患に対する予防が高い②母親と赤ちゃんに著しい健康被害が見られない―ことなどが示された。接種後の副反応については、接種部位の軽度の痛みや腫れ、赤みが報告された。横浜市立大学付属病院産婦人科診療教授で、周産期医療センター長の倉澤健太郎医師は「試験では、18カ国の母親と生まれた赤ちゃん、それぞれ約7000人分のデータを解析し、有効性と安全性が明らかにされた」と話す。
こうした結果を踏まえた上で、倉澤医師は「ワクチンの意義が伝わらないと、接種は広まらないだろう。そのために、効果や安全性も含めてためらいを生じさせない情報提供を行うことが不可欠。産婦人科医や助産師をはじめとした医療従事者への発信も重要だ」と強調する。

承認を取得したRSウイルスワクチン「アブリスボ筋注用」(提供写真、背景を加工)
◇ゴールはすべての赤ちゃんを守る
一方、森岡医師は、現在使われている抗体薬の投与時期にも課題があると指摘。「RSウイルス感染流行初期に投与を始めないと効果が出ない。これまで冬の風邪と言われていたが、ここ数年は夏にも感染者が出るなど、流行が一定しない。投与時期を見定めることが難しくなってきている」。
その上で「すべての赤ちゃんを守ることをしっかり考えなくてはならない。『入院して治すからいい』という時代ではないと思っている」と言葉を強める。
ただ、当事者である妊婦は「おなかの赤ちゃんに何かあると心配」と不安に思いがち。倉澤医師は「まずは妊娠していても使用可能なワクチンがあることを伝える。出産後の赤ちゃんの健康状態に関するフォローも必要だ。正しい知識が広まれば『子どものためにワクチンを打つ』という妊婦も増えると思う」と語る。
今後は定期接種化が目標と話す両医師。それには、どこで、誰が打つのか、費用はどうするのかなど診療体制の整備が急務だ。森岡医師は「今回の母子免疫ワクチンは、入院児の多くを占める基礎疾患のない子に対する、重要なアプローチになる」と期待する。(柴崎裕加)
(2024/04/25 05:00)
【関連記事】